2025.09.03
組織統合のタイミングで部門の垣根を越えた人材配置を実現するためにスキルを可視化

株式会社電通総研は創立50周年を迎え、Vision2030の実現に向けた成長加速と将来の発展基盤構築を目指し、新中期経営計画「社会進化実装 2027」を策定しました。この計画に伴い、従来の事業部制から本部制へと組織体制を刷新。新たに設置された「技術統括本部」に技術機能を集約し、部門の垣根を越えたスキル・ノウハウの共有と、柔軟な人材配置を実現する体制構築を進めています。
同社では「SkillDB」を導入したことにより、事業を横断した本部全体のスキル把握が可能になるだけではなく、中期経営計画にも掲げられている「高度デジタル人材の拡充」や「AI駆動開発による生産性向上」にも取り組んでいます。今回のインタビューでは、同社にて「SkillDB」の導入を進めるお二人に、その背景と導入のプロセスについて伺いました。
技術統括本部
技術統括推進ユニット
技術統括推進室 部長
綾部 豊
技術統括本部
クロスイノベーション本部
エンジニアリングテクノロジーセンター 部長
水野 和大
組織統合により7事業部1,200名が同じ組織に
あらためて今回の組織体制刷新の背景と、それぞれの部署の役割について教えてください
綾部さん(以下、敬称略):「電通総研 統合レポート2025」でも発表している通り、今回の組織統合には、大きく2つの理由があります。ひとつ目は、営業機能面での理由です。お客様のビジネスがより複雑化・高度化していくなかで、広範囲に及ぶお客さまの期待に対して、全社を横断して一貫した対応が可能な体制をつくる必要がありました。ふたつ目は、技術機能面での理由です。これまでは、金融や製造など、産業単位で事業部が分かれていたのですが、これらの部署を横断して人材のアサインメントができるようにすることで、より大規模かつ高度な案件への対応力を向上させることを目指しています。
そのような背景のなか「技術統括推進ユニット」の役割は、ドメインの垣根を超えた施策の企画・実施です。具体的には、人材の採用から、育成、パートナー管理、品質管理と幅広いテーマを扱っています。その施策の一環として、スキル管理システム「SkillDB」を導入し、スキルの可視化に取り組みました。

技術統括本部 技術統括推進ユニット 技術統括推進室 部長 綾部豊さん
水野さん(以下、敬称略):「クロスイノベーション本部」では、大きく3つの役割を担っています。ひとつ目は、生成AIなどを活用したエンジニアの生産性向上。ふたつ目は、AIやクラウド、セキュリティなど、先端技術のビジネス活用。みっつ目は、サービスやプロダクトを牽引できる人材、つまりはイノベーションを生み出せる高度デジタル人材の育成です。人材育成については、「技術統括推進ユニット」とも重複する部分もあるので、お互いに連携しながらスキル管理システム「SkillDB」の活用によるスキルの可視化に取り組んでいます。
それぞれの部門に散らばっていたExcelのスキルマップ
今回、スキルの可視化に取り組もうとされた背景や課題について教えてください
水野:今回の組織統合の前から、スキルの可視化には問題意識がありました。背景としては、近年のテクノロジー分野の複雑化と対応領域の拡大があります。たとえば、一昔前まではアプリケーションレイヤーの開発が我々の主要領域でした。それが現在ではクラウドの進化により、インフラ領域を含む幅広い設計・構築スキルが求められています。
そういったなかで、とくに若手からは「何から学べばよいのか分からない」という声が急増しています。ですので、広範囲にわたる学習内容に対して「どこから、どのような順番で、なにを学んでいけばよいのか」というものを提示できるようなロードマップのような存在が必要だと感じていました。
しかしながら、企業としては、人材育成の大半がOJTを頼りにしている部分があり、より個に依存しない再現可能な育成体制を構築できないかと考えていました。
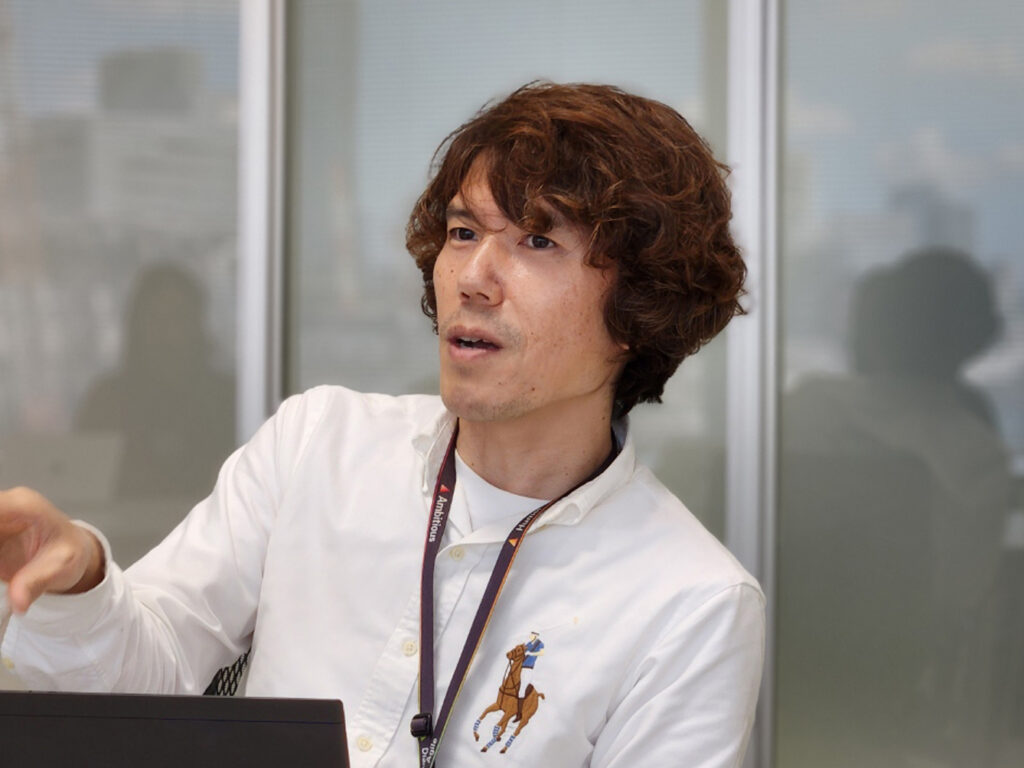
技術統括本部 クロスイノベーション本部 エンジニアリングテクノロジーセンター 部長 水野和大さん
綾部:柔軟なアサインメントの実現と、再現性のある育成体制の構築。この2つを実現させようとしたときに、スキルマップを作成し、社員のスキルを定量化することを考えました。しかしながら、そこには3つの課題がありました。
ひとつ目は、各部門で求められるスキルセットがバラバラということです。実際、「SkillDB」導入前にも、スキルマップを作成する取り組みは各部門でも進められており、それぞれの部門が、それぞれのフォーマットでスキルマップをExcelで作成・運用している、という状態でした。そこから、共通する要素を抽出して、強化するべきポイントを整理する必要がありました。この課題解決には、各現場との綿密な対話が不可欠でした。
ふたつ目は、スキルマップのベースとなるスキルデータについてです。ここについても、以前、社内で政府が定めるスキル標準をもとに、スキルを可視化しようとする取り組みがありました。しかしながら、実際に可視化していると、スキルの粒度やレベル分けが、汎用的すぎて抽象度が高く、現場で必要なスキルを十分に表現することができませんでした。
みっつ目が管理システムについてです。上記の問題があったため、スキルデータを内製し、タレントマネジメントシステムを活用してスキルを管理しようという時期があったのですが、構築やデータをメンテナンスするコストが高く、すぐに挫折してしまいました。実際に、以前構築したシステムは、インフラコストのみでも、現在「SkillDB」に支払っているコストよりも、割高でした。
水野:上記のような経験もあったので、海外のサービスも含めて検討していたのですが、なかなかよいものに出会えていませんでした。そんななか、たまたま社内で紹介してもらったのが「SkillDB」でした。いままで自分たちで作成していたスキルのデータセットがプリセットとして用意されているため、スキルマップの構築・運用コストを大幅に下げることができると思いました。また、スキルと学習教材が紐づけられているため、スキルの可視化と育成体制の構築を目指す我々にとっては、ぴったりなサービスだと感じました。
経営のコミットメントとプロジェクトメンバーのアサインが成功のポイント
今回の導入プロジェクトについて教えてください
水野:まず導入プロジェクトについては、社内の3名の少人数のワーキンググループで検討を開始しました。大事なことは、「経営としてのコミットメントが、明確な言葉で示されていること」です。私たちの場合でいえば、「人材育成」は経営にとって大きな注力テーマでした。このように、経営が明確にコミットしていることが、プロジェクトを進めるうえでの出発点となります。
つぎに「誰がやるのか」という点です。これについては、経営・ビジネスの要件を、技術的な要素まで噛み砕ける人材がやるべきです。ITアーキテクトは、どのような単位で分類分けするべきなのか。生成AI活用とは、どのような単位でスキル習得するべきなのか。そのような技術的なバックグラウンドがあるメンバーは、課題の多いプロジェクトを任せられるような、社内でも高度な技術者になると思いますが、そういったテックリード的な立場の人材が工数を割くべきです。
サービスの検討、導入判断については、小さなPoCからスタートしました。まずは特定の部署で必要なスキルマップを構築できるのか、というスコープからスタートし、それを技術統括全体で利用可能なのかと検証を進めてきました。
具体的には、特定の事業部で活用されている技術を棚卸ししたうえで、フロントエンド(React、Vue)、バックエンド(Java、Python、TypeScript)、クラウドアーキテクト(AWS、Azure)、モバイルアプリケーションエンジニア、データサイエンティストなど、全体で共通する必要な技術要素を抽出しました。我々ワーキンググループのメンバーだけでは、判断できない専門領域については、社内の専門家にも協力してもらいながら、スキルマップを作成しました。
スキルマップの作成にあたっては、テックピットさんにテンプレートを用意してもらえたので、必要最低限な修正で構築することができました。例えば「生成AI活用」のためのスキルマップについても、「SkillDB」上でテンプレートが用意されているので、スムーズに構築作業を進めることができました。
また運用段階でも、他社の運用やデータ活用事例について伺うことができたり、弊社内での説明会に参加いただけたりと、細かな改善要望などにも素早く対応いただけて助かっています。例えば、細かなデザイン面でのフィードバックや機能追加の要望についても、翌週や翌月には実装される機能もあり、迅速な対応に感銘を受けました。
プロジェクトをリードする人材の質・量が可視化
導入の成果と今後の期待について教えてください
綾部:プロジェクトをリードできるような人材を質・量ともに可視化するための基盤が整った、というのが成果の一つです。今後、この取り組みを進めていけば、部署を横断して、必要な技術要素をもった人間が、どれくらい、どのレベルに分布しているのかを理解することができると手応えを感じています。また、スキルが可視化されただけでなく、スキルレベルにあわせて、学習教材のレコメンド機能があることで、可視化から育成までをシームレスに連携できる体制を構築できたことも一つの成果です。
今後は技術領域だけではなく、プロジェクトマネージャーなど、より幅広い職種についてもスコープを広げることで、より会社全体のポートフォリオを可視化できればと考えています。

ダッシュボード機能のイメージ
水野:スキルの可視化だけではなく、「投資対効果」の可視化による、経営の意思決定まで繋げられたらと考えています。個人の育成が、どのように組織への貢献に繋がったのか。単に社員一人あたりの売上・利益だけではなく、サービスやプロダクトへの貢献など、会社のイノベーションにどのように貢献できたのか、まで繋げて語れるようにしたいと考えています。
そのなかでのテックピットへの期待は、この業界のデファクトスタンダードになってほしい。このサービスを利用する企業のコミュニティをつくって欲しい、ということです。
一言でいうと日本の将来を憂いています。クラウドやAI、セキュリティなど先端分野では、慢性的に人手が不足しています。この状態を放置したままだと、経済産業省のレポート(2025年4月30日公開)だと、2035年までに18兆円を超えるデジタル赤字を計上するとも発表されています。そういった状況を打破するためにも、私たちは日本経済をエンジニアから元気にできる会社を目指しています。いま社内にいる人材を、高度人材まで育てあげ、活躍する場を提供し、世の中に価値を生み出していく。そのためにも、今後も「SkillDB」を活用し、この目標の実現に取り組んでいきます。
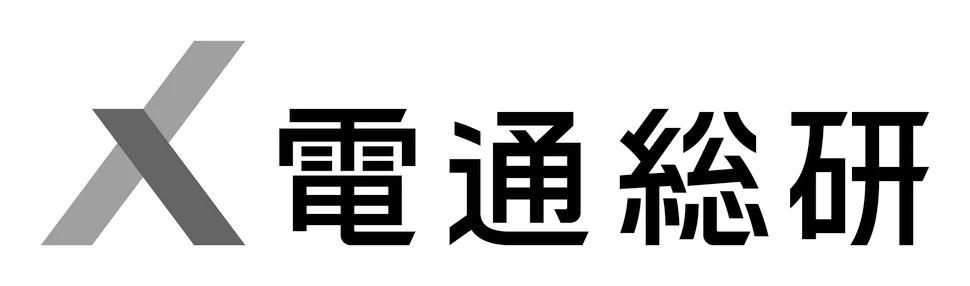
社名
株式会社電通総研
事業概要
システムインテグレーション、コンサルティング、シンクタンクの機能連携による、社会や企業の変革を支援するソリューションの提供
従業員数
4,413名(2024年12月末現在)
企業URL
https://www.dentsusoken.com
目次
▶︎ それぞれの部門に散らばっていたExcelのスキルマップ